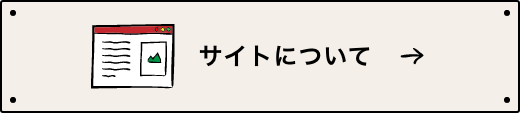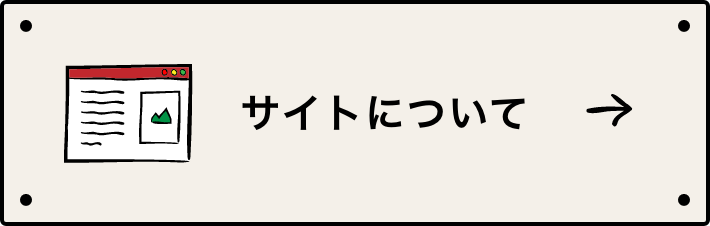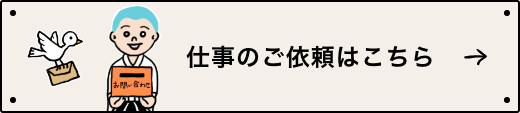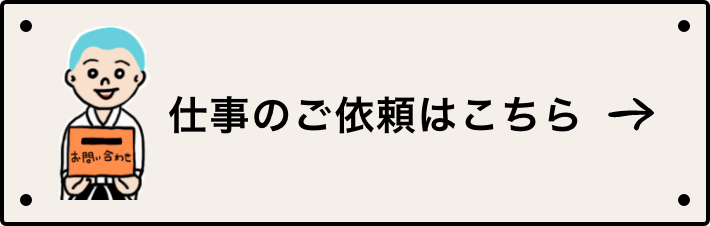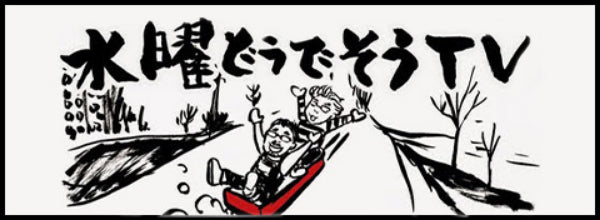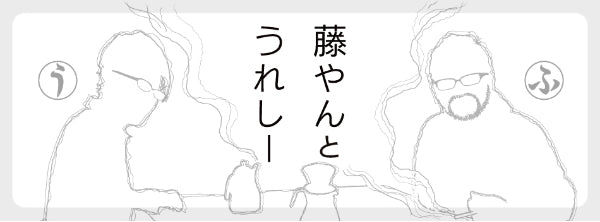世間とはかけ離れた視点(D陣日誌:嬉野&藤村)
(2025/02/25)
嬉野です。
さて、今年2025年は、ヒゲマラソン部にとっては10年目の大阪マラソンだったのですが、周年のその大会にヒゲマラソン部部長は不出場。副部長は時間内にゴールできずに足切りとなりバスに乗せられるという、まったくもっての体たらく。
しかし、これだからこそ、あの人たちから目が離せない。
私としても「応援📣」ということで( まぁその応援にしたって私は言われるがまま無批判に毎年通い詰めて10年なんですが )、天満のアパホテル前で今年も応援隊の列に加わっておりましたが、先頭集団の走りの速いこと!
あれではいけません。
あんなに速く走られては応援している方の気持ちが盛り上がらない。
目の前をあんなにあっさり通過されては、私だって10年も応援に通いませんし、部長、副部長だってあんなに速く走れたら10年を待たずにマラソンなんかやめてたはずです。
やっぱりランナーは、我々応援の前に、ヘロヘロになって現れてくれないと応援隊としてはマラソンの醍醐味が感じられない。そこへ行くとうちの部長も副部長も、我々応援隊が沿道に立てました幟にすがりつくように吸い寄せられて来ますから、応援としては堪えられない。この弱りようこそがマラソンランナーです。
やっぱりね、毎年うっかり記録を更新してしまうようでは我々応援の期待に応えたことにはならない。
マラソンランナーであれば、とにかく心底疲弊して、応援している沿道の我々に、「あの人たち、なんであの程度の実力で毎年出場してはるんやろう?」と、疑問に思わせるぐらいじゃなきゃいけない。
つまり、人間というものは、自分らと遊んでくれる人が好きなんです。そこは大人になっても小さな子供と同じです。同じレベルまで降りて来て、一緒に、力を出し切って遊んでくれる人が好き。
そういうことになると思うんですね。
そういう意味では、大阪マラソン、走ってから10年目というのに、いまだこの体たらくというのは、実に寿ぐべきことであり、まだまだ、うちの部長も副部長も皆さんと遊ぶ気充分という気迫を感じました。
変わらないふたりには驕りがない。
そして性懲りもなく来週も竹田で走るという、マラソンを舐め切ったこのスケジューリングで、こっちもそろそろ10年です。
こういうことの積み重ねが、ヒゲマラソン部という集団が、マラソンの楽しみ方というものを勝手に独自の文化に捻じ曲げてゆくわけです。
宗教で言えば、メジャーな信仰から抜け落ちてしまって、もはや異端、異教、邪教と変貌して行くように、マラソンの楽しみ方というものを、土俗的に横滑りに発展させて後戻りもできない独自のものとしていくという、文化的にも実に目が離せない展開となっておるわけですから、みなさんも、そこのところへ注力して、今後とも信心していただければ、まだまだ人生、お楽しみいただけるということで、副部長がバスに収容されて終わるという、10年目の大阪マラソンにふさわしい金字塔を建てたな、ということで、長く記憶に残る体たらくを成したと思えば、たいへんに宜しゅうございました。
立派、立派。
ということで日誌です。
流れとしては上の記事とは、いささかも関連性がない話で恐縮ですが。「クレイジージャーニー」に、たまに出てくる呪物コレクターの田中さんという人が、この頃、私は気になっていて。
この方は関西で怪談師をしていて、稲川淳二さん主催の怪談師王座決定戦みたいなやつに、当時、ゆいいつの素人枠ながら出場してみたら芸人さんらを押し退けて優勝してしまったという人らしく。
近年、東京に出てきて現在は安アパートに住んで、狭い自室に世界中から集めた呪物が足の踏み場もないほど並んでいて、それを私は、「クレイジージャーニー」で見て、田中さんのお部屋から醸し出されるビジュアルの凶々しさに毎回戦慄を覚えるわけですが。
なんで、あんなおっかない呪物とかを収集して、あんなおっかないものたちに囲まれて生活できるのか。
私などには理解不能なんですが。
でも、なんでしょう。一見、風采の上がらない田中さんが( いや、今となってはあの風貌だからこそ私は田中さんが信頼できたりもしているわけなんですが、まぁそんな田中さんが )、呪物1つ1つの因縁話もしてくれて、当然その話だって聴くだに身の毛もよだつ凶々しさなわけです。
なのにどういうんでしょうね。田中さんの口から聴いてますと、そのうちそれほど怖くないように思えてくる。
それが不思議で。
なんでしょうか、ある意味、人と接するときの距離というんでしょうかね。上手く言えそうにないんですが、田中さんから呪物の「いわく因縁」を聞いてますと凶々しいものにしか見えない呪物にも日常性が帰ってくるとでも言えばいいのか。なんか呪物の見てくれが普通じゃないからと言って、内実は、そうまで凶々しくもないんじゃないかしらと段々思えてくる感じがしてくるんですね。
「これは亡くなった人の人骨で作った笛なんですけど( 人骨の笛?ですよ。誰とも知れない死んだ人の骨で作った笛ですよ。こんなことを聞いた時点で、よくそんな笛をコレクションするよな!と思うんですが その先の話を田中さんはこう続けるのです)、なんかですね、この人、生前、たいそう不幸な方だったらしくて。そうすると、生前この人が体験できなかった幸福というものは使われずにこの骨の中に貯められているらしくて。だから、この人の骨で作ったこの笛を吹けばね、この人が使わなかった幸福が、笛を吹くたびに世の中に撒かれることになって、みんなが幸せになれるみたいなんですね」と、そんな話をしてくれる。そういう物も呪物の1つなんですね。
そんな由来を聴きますとね、呪物やら呪術やらの根っこにある考え方というのが窺い知れるようでね。つまり、単に誰かを呪うとか不幸に陥れるとかいうだけのヤバい物ではなくて、それこそ人間社会に良い影響を与える助けにもなる。
なるほど、知らないからこそ得体の知れない気味の悪いビジュアルだけを見て、それだけでこっちは肝が縮み上がってしまうからバイ菌みたいに見えてしまって、バイ菌なら見たり触ったりそばに置いたりして関わるだけで禍いが自分たちに感染してくるじゃないかと、勝手な考えに陥りそうにもなるんですけど、
田中さんの話を聞いてると、呪物は病原体のように人に祟るとかじゃない。むしろ人間の生前の運と不運をバランスして考えて、生前のその人の運と不運の偏りに目をつけて、生前に不幸過ぎた人なら、その人が使わなかった幸福はどこへいったかとさらに考え、その人のことを、「この人は生きてるときに福を使わなかった人なのだ」と喝破するわけです。
そして、そんなにも不幸な人生を送った人が残した物を祀ったならば、その人が使わなかった多くの福を、後々を生きる我々が使わせてもらえるたろう、とでもいうようなね。不幸な人の人生すらも前向きに捉えて崇めれば、残された自分たちに幸福をもたらす結果をもたらすのだという思想ですね。
そこには、生前の不幸を、死後、恨みに変化させず。崇めて祀り、敬意を表することによってその人の人生の不幸をチャラにして、尚且つ後に残った者がプラスへと転嫁させ、その幸せを頂こうという、幸運を残さず食べる的な気質が呪物信仰には内在していると思えてくるわけです。
このように考えれば、世界には、ただ凶々しいもの、ただ忌避しなければならないものなど本来はなくて。
あらゆる物の価値は、辻褄を合わせ、筋道を通せば、マイナスもまたプラスに変えてしまえるのだ、とでも言うような。呪物というのは、そのようなプラス思考に根差した思想であり、運と不運、強力と無力といった生きてる人間たちの世界で対立しているプラスとマイナスを、死後、チャラにして、尚且つ全部プラスの方へ昇華させてしまおうという、物事をどこまでも前向きに見通してしまう信仰のようにも思えてくるわけです。
そうしたときに田中さんは、その呪物にまつわる、その呪物が引き起こしてしまった祟りの話とかもしてくれるから、それをコレクションしてしまった田中さん自身だって「これは、本当に注意して祀ってないと祟られると言われてますんで」とか言いながら、それでもやっぱりコレクターの血が騒ぐのでしょう、手に入れてしまって部屋に置いているわけで。つまり田中さんにとっては祟られることはリスクなんだけど、コレクターとしては、手に入れた呪物に祟られるんなら祟られたで、祟られた体験ごと受け入れるにやぶさかではない、みたいな。世間とは軸のズレた呪物に対するコレクター根性が見うけられて、それもまた呪物に微笑ましい一面もあるように見せてくれる一助ともなって、私に呪物に対する認識を新たにしてくれるわけです。
なんだか、まるで、大泉洋さんをびっくりさせたいからと、彼をジャングルにつれて行くんだけど、結局、同じように自分たちも鬱蒼としたジャングルに分け入ってウンザリして、「来るんじゃなかった」と後悔している「水曜どうでしょう」の人たちを彷彿とさせるようでもあり、親近感を得るわけです。
そんなこんなで、田中さんには他のオカルトの人たちとは違うスタンスを感じて私は近年ファンですね。
ちょっと前に、アマプラでドキュメンタリー映画「続・三軒茶屋のポルターガイスト」ってのを見たときね。人ならざるものの手が床から生えてくるという奇妙なアクターズスタジオが三軒茶屋にあって。床から生えてくるその不思議な手の噂を聞きつけて訪れた人たちの誰の目にも、その手があまりにもハッキリ見えすぎるものだから、
「え? なんだろう」「え? これってなに?」と、訪れた誰もが、床から生えてきた手を見て奇妙に思って混乱し、出現してしまった「人ならざるもの」と、なんとかコミュニュケーションしたいとコックリさんとか試みるんだけど。
そこに超心理学を研究してる大学の学者先生も呼ばれて来たは来たけど、「どうですか?」とみんなに問われて、「どうもなにも、こんなものはインチキだよ!」と途中でカンスケに怒りはじめるという顛末がありましてね。科学者の人は集まった中の誰かがトリックを弄してみんなを騙してるだけじゃないかとお怒りで。私は、床から出現した手よりも、その科学者先生の唐突な怒りの方にびっくりしまして。
なんでしょう、「床から出現してしまった手」なるものをその目で見て、その存在を疑えず信じて集まっている人たちがその場に多くいらっしゃるのに、「科学は、嘘は嘘として暴く。それが正義なんだ!」と、コミュニュケーションは、疑うことからしか始められないと言わんばかりの、「認める、認めない」という厳格さで、「真実はひとつ」だけと規定して、真実が証明できなければ、それ存在できないと審判を下すジャッジマンとしての立場でしか他人と交れないと言いたげな科学信奉者の人が
私にはなんだか野蛮に見え。
それが、くだんの田中さんに見えないことも、私にはホッとできて気持ちが良いわけです。
だって、相手を疑うところからでは人と人とのコミュニュケーションは成り立たないでしょう。
そこを考えると、呪物に祟られることすら甘んじて受け入れてでも収集したいというコレクター根性の田中さんの方が、出現してしまったものに対する愛を感じるようでもあり。
そもそも、「認める、認めない」という厳格さで人と接していては、そこに愛が見えないだけに誰とも知り合えないでしょうから、田中さんみたいな人を見てますと私は大変気持ちが良いわけです。
人間なんて、気持ちの弱いものですから。「この呪物を持っていると祟りがあります」とか言われたら、僕らはついつい信じてしまって自分の方から祟りに遭いそうな、進んで不幸になってしまいそうな、人生を終わりたくなるような気持ちになって行くもんですよ。人間が不幸になるきっかけだって、その多くは自分から「ダメだ」と思ってしまう自滅だったりしますからね。
呪物は、科学とは違って、そんな人間の弱い気持ちに作用する物でしょうから、気味が悪いと思ったら自分で勝手に肝が縮んでしまうし、他人から、「おまえは不幸になる」って言われたら、なぜか、知らず知らず自分の方から進んで不幸になり始めるのが人間だったりするわけです。
結局、人間の根性には自分の方から負けに行こうとするところがあるわけですね。
田中さんはそうした、人間が本来持つ弱い資質を、「それって、ありますよね」と、肯定して、受け入れるところが前提になっているようですから、呪物を非科学的だという理由では否定などしないわけです。
たとえばクレイジージャーニーのアフリカロケで、「呪術相撲」とか言う、格闘戦なんだけど、腕力に加えて呪術や呪物を呪術師に与えられ、闘う両者共にその呪物を身に纏って相手の力を封じ込めたりもするんだ的な話を現地で聞かされても、対戦相手も同様に呪術の効力を信じる文化の人であるなら彼も当然相手の呪物が気になっちゃったら勝手に気持ちで負けてしまって、力が萎えてしまう。そうなれば本来の力が出せなくなる。だったら相手の呪術や呪物で自分の力が封じ込められてしまったりもするわけでしょうからね〜的に田中さんは納得する。
そんな田中さんが私は、近年、気になるわけです。
何かですね、呪物コレクターである田中さんが、自分の集めた呪物コレクションの1つ1つの由来を愛ゆえに鵜呑みにして信じて。呪物1つ1つの性質を受け入れて、その扱いを生真面目に気にして、呪物1つ1つと一定の距離を置いて接しているところが、なにか人と向き合うときに大切なこととも通底するように思えて、呪物信仰というものと、コレクター根性というものは、この世で生きる他人を意識して、そこに愛を感じて、そこから他人を大事に思うことに通じるようにも思えてきて、その辺りも田中さんを見てて気持ちがよろしいのです。
----------------------------------
(2025/02/25)藤村
嬉野先生の日誌で、ヒゲマラソン部を語っておられました。
部長、副部長の体たらくな結果があるからこそのヒゲマラソン部であるという「評価」を、世間とはかけ離れた「視点」で語っておられて、いや、感服いたしました。
我々は日常、「自分の視点」ではなく、知らず知らず「世間の視点でのモノの見方に自分を合わせる」ようにしていることが往々にしてある。
マラソンであれば、去年よりも記録が伸びたか否か、初マラソンでそれなりの記録を残したか否か、そういう分かりやすい短絡的な視点が、すなわち「世間の視点」で、それに合わせて、ただ「良かった」「ダメだった」と言葉を吐いている。
短絡的でなければ世間のひとには分かってもらえないから、自ずと「世間の視点」というのは、知的レベルの低いものになってしまう。
その低レベルさを、嬉野先生はわかっていて、独自の評価を下している。
こんな評価を下せる批評家はいま日本にはいないですよ。
ひろゆきくんもホリエモンも、他の人たちも、「世間の視点に対して、反対するか、賛成するか」が主な論理であって、嬉野先生は「世間の視点とはまったく無関係なところに価値を見出している」んです。
そのあとに続いた田中さんのお話も、実は正月にウチの長男が「いまこれにハマってる。おとうも見た方がいいよ」と勧めてくれていた動画で。そこには、世間とは全くズレた評価があるわけで。
ここにある嬉野先生の日誌は長すぎて、いまはみんな全部読めなくても、後世になって評価されるものであろうなと思います。