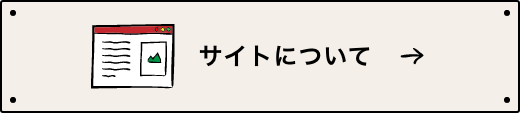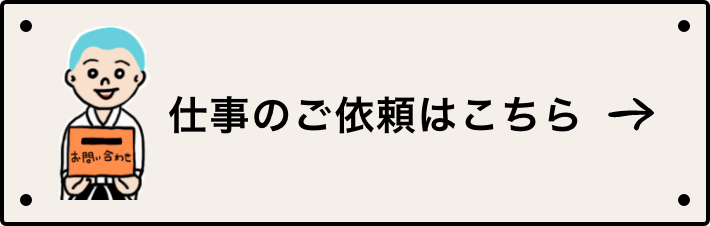もしもあのシーンで(日曜更新D陣日誌:嬉野)
嬉野です。小津安二郎監督の「晩春」という映画は、父ひとり娘ひとりの父子が、早くに亡くなった母親の代わりに幼子のときから手塩にかけて育てた愛娘が大輪の花のような年頃の娘に育ちながらも、ふと気づけば適齢期をとうに超えてしまい、うかうかする間に行き遅れては大変と、好きな異性もいなかったのに、思い切って見合いさせ、嫁に出すまでの父と娘の長閑な日常を描いた物語なんですが、「なんか、父と娘なのにイチャイチャし過ぎなんじゃないですか?」と、朝っぱらから私に聴く人がいたもんで。
そしたら私も、たまたま昨晩、ミケランジェロアントニオーニ監督の「情事」という、失踪した親友を探している女子と失踪した親友の恋人とが、失踪者を探している2人であるのに、映画を長々見ておりますと「なんだこの2人は、親友や恋人を探してる2人のはずなのに、なんかイチャイチャしたがってるんじゃないのか」と思ったことと、奇しくも合致するところがあるように思えたものですから、ちょっと考えてみることにしたわけです。つまりその。映画の得意分野というものをですかね?
映画「晩春」は、誰がどう見ても、閑静な北鎌倉に住む、大学教授とその美貌の娘の暮らしぶりを描いた上品な作品なんです。昭和24年の公開ですから「戦争も終わったし、とにかく良かったね」的な気分の中で、そこそこお金のある中流階級のしかも戦災で家も焼けずに残った北鎌倉辺りの家庭から順に穏やかな日常を取り戻したことを悦ぶ暮らしぶりが画面の中に丹念に描かれてもおりますから、そういう戦後すぐの中流家庭の暮らしぶりを、当時、映画のスクリーンに眺めることは敗戦の焼け跡生活から始めさせられた庶民には、まだ手の届かなかい贅沢な日常だっだけど、そのステキな日常の暮らしぶりを映画の中に見て憧れの目で追体験して我がこととなし、自分の置かれた戦後の現実を束の間忘れて憩いたいという、そういう欲求の対象として当時の映画はその役割を果たしていたとも思われるわけです。
なんですが、それでもこの「晩春」という映画はたしかに見てるとなんか変なんです。結婚前に父(笠智衆)と娘(原節子)で、2人だけの水入らずで最後に京都旅行をしようということになるんですが、この旅行中に娘役の原節子さんの美貌がどんどん妖艶に照り輝いて、もうもう、そうとうエロいわけです。
その旅の中で娘が父親に言うセリフとも思えない、なんだかイチャイチャし過ぎちゃってて「なんだ、どーした」と見ているこっちが恥ずかしくなって違和感を覚えるほどの娘のセリフなんです。
まるで婚期を逃して行き遅れそうな年齢になろうとしている28歳の娘が、本当のことを言えば、正真正銘に実の父親にゾッコンで恋をしていて、その証拠にいまや妖艶なほどの美貌をテラテラと父親の前で惜しげもなく広げて、しかもそこは旅館の床の上というヤバい場所で、そこで浴衣に着替えた娘は、それと知らずに猛烈に父親にアタックしているように口説いているのです。そんな妖艶な原節子さんの揺れる眼差しと、赤い唇がぐいぐい笠智衆さんを恋情の沼に誘い込むように語り出すのです。「この私の熱烈なる恋心を受け止めてほしい」と、あろうことか見ようによっては実の父親に迫るシーンとみてとれて、思わず「どーした!」と、受け止めきれないほどの恋心を原節子さんは惜しげもなく笠智衆さんに晒していることに気づかされるわけです。
つまり、父と娘の、つましい健気な物語のはずが、途中から、どこでどうなったのか父と娘の道ならぬ恋として見えてしまうのです。それだけで「晩春」は、いきなり大恋愛映画の様相を呈してくるわけです。
しかも2人は父娘。となればそこには道ならぬ変態性愛が加味されてくる、ことになるわけです。そんな映像展開なので、古来より「晩春」を、変態性愛映画と認識する映画ファンは多いと聞きます。
ですが事実、そういう道ならぬ目で「晩春」という映画の父と娘のやりとりを見れば本当に全てがしっくりくる。もちろん、全てはたんなる映画の中の絵空事ですが、とはいえ、こうまで間近で原節子さんのあの美貌に迫られては、そしてその熟れて落ちそうな娘盛りの原節子さんにあぁまで熱を帯びた言葉で口説かれ続けられては、「そうじゃないんだ、それは違うんだ、いや、後できっと違うということが分かるんだ」と、父親の笠智衆さんとしては、原節子さんのその溢れる気持ちをいなして、そらして、最後まで節度と常識をもって自分は娘とは距離を保って立っていなければと自分に強い意志を課すことで精一杯だったであろう父親の笠智衆さんの気持ちをおもんばかれば、間違いなくこれはもうもう拷問です。地獄です。そういう目で映画「晩春」を見ると、もう、そうとしか見れないのです。
おそらく笠智衆さんの演じた父親は、本音を言えば、あの状況ですから娘である原節子さんの熱愛をもう受け入れてしまいたいと幾度思ったことか。しかし、そこは意志の力で、気持ちを抑えることに必死だったに違いないと思われて。見ているこちらとしては息苦しくなるわけです。
しかし、こうした角度から「晩春」を見はじめると「晩春」は立派に変態性愛映画になるわけで。そんなバカな。そう思う賢明なる諸兄氏も多々おありになるでしょうから、これ以上は言いませんが。後年、小津安二郎監督も亡くなられ、笠智衆さんも晩年になられた1980年頃。笠智衆さんはインタビューの中で次のような重大な証言をされていました。
「『晩春』という、あの映画のラストシーンを撮影するとき、原節子さんを嫁がせて結婚披露宴を終えて、誰も待っていない北鎌倉の家に帰ってきて。暗がりの中で部屋の灯りをつけて、独り、私は椅子に腰を下ろして、手近にあったリンゴの皮を剥き始めるんですが。そのとき小津先生は言われたんです。『笠さん。悪いけど、そこで号泣できないかな』って。私は先生の言葉にひどい違和感を覚えて『そんな、先生。娘を嫁に出したくらいで男が号泣するなんて、そんなことは、私には出来ません』と、反射的にそう言って断ってしまったんです。しかし、後にも先にも小津先生のおっしゃることに従わず断ってしまったのは、あのときだけです。先生は『そうか。わかった』と、あっさり引き下がられました。でも、今あらためて思うと、あのとき僕が小津先生のおっしゃられた通り、あのラストでもし号泣していたら、あの映画は、まったくな違う味わいのものになったように思えるんです」と、なんか、そんな重大な証言を笠智衆さんはされていたんです。
そうなんですよ。あの「晩春」という映画を父娘の話としてだけ見るなら、それは笠智衆さんの違和感が正解なんです。でも、変態性愛映画として見るならば小津安二郎監督の要求が正解なんです。そして、一度「晩春」を見て貰えばわかるのですが、もしラストシーンで笠智衆さんがりんごの皮を剥きながら、不意に号泣しだして慟哭の声を上げて終わったならば、あの「晩春」という映画は、とんでもない傑作になったことだろうと惜しまれてならないのです。
そして今そのことを思えば、映画「晩春」は、監督・小津安二郎さんの中では、変態性愛映画としての一面でも演出されていたのだろうなと、思われてくるのです。
いや、私がここで、あえて「変態性愛」と書いたのは、それがこの、人の社会ではけして許されないとされる間柄だというだけのことからです。
ミケランジェロアントニオーニ監督の映画「情事」がそうであるように。親友が失踪したのに。恋人が失踪したのに。その失踪した娘を探す2人であるはずなのに。その2人が捜索旅行の中で男と女として惹かれ合うなんて。そんなことは許されない。2人が惹かれ合うことは社会的に許されない間柄とされるのです。それなのにそんな2人が関係を持って仕舞えばケダモノと言われてしまうでしょう。でも、映画監督はえてしてそういう男女の揺れる心を描きたいのです。なぜなら映画という表現は、葛藤して揺れ動く心に翻弄されるような恋人たちの葛藤を見せることに適している表現手段だからです。
だからこそ、そういう「変態性愛映画」的目線で探せば、実にたくさんのタイトルが思い浮かぶのです。そして、そのほとんどがなぜか傑作、名作なのです。
みなさんもこの機会に「晩春」を「変態性愛映画」として一度ご覧になってはいかがでしょうか。そして、ラストシーンで笠智衆さんが突如として号泣して慟哭の声を上げたなら、あぁ、どれだけの名作になっていただろうと、そこも想像して見ていただきたいわけでございます。お粗末さまでした。
(2022年8月21日 嬉野雅道)