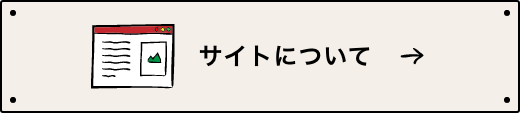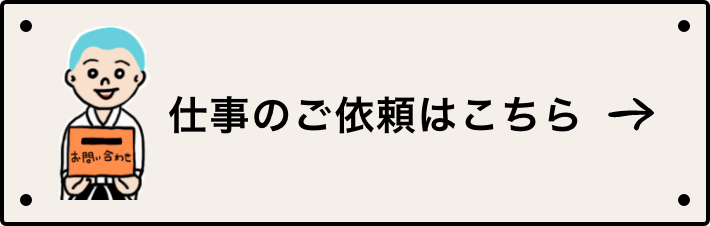あるはずはないけれど(水曜更新D陣日誌:嬉野)
嬉野です。
この頃こそ、そんなに思うこともなくなりましたが、少し前までは、なにかと天気の良い午後に新幹線の「こだま」に乗って長い時間をかけて京都から東京へ向かったりするときには、流れてゆく車窓の景色を眺めるうちに不意に良い感じに侘しくて平和そうな佇まいの田舎町が目の前に展開すると、きまって「ひょっとして、ここら辺のどっかの家で、亡くなって久しい、お父さんとお母さんが、今も仲良く暮らしてるんじゃないのかなぁ」と、勝手に妄想してしまうときがあったんです。
新幹線の車窓に流れる景色なんて、すぐに流れ去ってしまうんですけど、それでもそんな風景を目にしたときは必ずそんな風に思ってしまって。きっと町の名前を教えられても、もちろん知らないし、聞いたことも行ったこともない町に違いないんでしょうけど。それでも、その時刻の穏やかな光の具合が私にそう見せるのか、すぐ近くに田んぼが広がっていたり、こんもりした森に小さな神社が見えたりして、どこか自分に好ましさを感じさせる風景というものがあるのでしょうね。そういうのを見てしまうと、ふと両親が、この町のどこかで二人きりで仲良く暮らしていそうに思えてしまって、次には居間でお母さんがお茶を淹れていたり、相撲が好きだったお父さんがNHKの相撲中継を見ていたり、二人で車を出して近くの町まで買い物に行ったりしているような幸福そうな夫婦の情景が勝手に浮かんでしまって、景色が流れ去ってしまったあとで、いつか新幹線を降りて、てくてくこの足で二人が暮らしている家を探して訪ねてみたくなるような、そんなおかしな気分になることがありました。
脚本家の山田太一さんが書いた「異人たちの夏」みたいな話ですよね。
あれも50近くなって、離婚して、独り身になった脚本家の男が、ある日、当てもなく入った浅草の演芸場で見覚えのある後ろ姿の男を見つけて、あとをついていってしまうんだけど、そのうちその男が、どう見ても自分が12のときに35歳で亡くなってしまった寿司職人だった自分の親父に思えてしまって、こんなに似ている他人のそら似というものがあるのかなと思っていると、不意にその男がくるりと振り返って、「おう。おまえ、うち、寄ってくだろ?」と当たり前のように話しかけてきて、そのまま不思議な懐かしさに魅せられたように、ついつい男の誘うままアパートまでついて行ってしまい、2階にある部屋の前まで来て「ここだよ。ほら、上がれ」と勧められて。「いや、今日会ったばかりの人の家に上がるのはやっぱり図々しいから」と、まだ遠慮がちなことを言いながらも、心のどこかではひょっとするとという期待が消せないでいると、果たして部屋の奥からにこやかに女が顔を出して「あら、よく来たね。早くお入り」と親しげに部屋に入ることを促してくれる、その女の顔が親父と一緒に亡くなってしまった母親でという話。
12歳で両親を亡くして以来、ずっと祖父母や叔父さん夫婦に育てられてここまで生きてきた男が、50近くなって、自分よりも年若い両親と、2人だけで暮らす部屋に招かれて再会するといった話が思い出されてくるんですよね。
なんでしょうね、自分が住み慣れた色濃い記憶のある実家で再会するというのではないという、そのシチュエーションが余計に、お互い「あれからどうしてた?」という穏やかさを連れてくるようでね。過去に戻って会うんじゃない、今という地点でお互い再会するというところがね、なんとも心慰められるんでしょうね。
そんなあるはずもないことが、それでも、あったとしても不思議はないと、私にはやっぱり思えてしまうんですね。
私が昔から怪談話が好きな理由も、きっと、この辺りにあるのかもしれませんね。
この頃こそ、そんなに思うこともなくなりましたが、少し前までは、なにかと天気の良い午後に新幹線の「こだま」に乗って長い時間をかけて京都から東京へ向かったりするときには、流れてゆく車窓の景色を眺めるうちに不意に良い感じに侘しくて平和そうな佇まいの田舎町が目の前に展開すると、きまって「ひょっとして、ここら辺のどっかの家で、亡くなって久しい、お父さんとお母さんが、今も仲良く暮らしてるんじゃないのかなぁ」と、勝手に妄想してしまうときがあったんです。
新幹線の車窓に流れる景色なんて、すぐに流れ去ってしまうんですけど、それでもそんな風景を目にしたときは必ずそんな風に思ってしまって。きっと町の名前を教えられても、もちろん知らないし、聞いたことも行ったこともない町に違いないんでしょうけど。それでも、その時刻の穏やかな光の具合が私にそう見せるのか、すぐ近くに田んぼが広がっていたり、こんもりした森に小さな神社が見えたりして、どこか自分に好ましさを感じさせる風景というものがあるのでしょうね。そういうのを見てしまうと、ふと両親が、この町のどこかで二人きりで仲良く暮らしていそうに思えてしまって、次には居間でお母さんがお茶を淹れていたり、相撲が好きだったお父さんがNHKの相撲中継を見ていたり、二人で車を出して近くの町まで買い物に行ったりしているような幸福そうな夫婦の情景が勝手に浮かんでしまって、景色が流れ去ってしまったあとで、いつか新幹線を降りて、てくてくこの足で二人が暮らしている家を探して訪ねてみたくなるような、そんなおかしな気分になることがありました。
脚本家の山田太一さんが書いた「異人たちの夏」みたいな話ですよね。
あれも50近くなって、離婚して、独り身になった脚本家の男が、ある日、当てもなく入った浅草の演芸場で見覚えのある後ろ姿の男を見つけて、あとをついていってしまうんだけど、そのうちその男が、どう見ても自分が12のときに35歳で亡くなってしまった寿司職人だった自分の親父に思えてしまって、こんなに似ている他人のそら似というものがあるのかなと思っていると、不意にその男がくるりと振り返って、「おう。おまえ、うち、寄ってくだろ?」と当たり前のように話しかけてきて、そのまま不思議な懐かしさに魅せられたように、ついつい男の誘うままアパートまでついて行ってしまい、2階にある部屋の前まで来て「ここだよ。ほら、上がれ」と勧められて。「いや、今日会ったばかりの人の家に上がるのはやっぱり図々しいから」と、まだ遠慮がちなことを言いながらも、心のどこかではひょっとするとという期待が消せないでいると、果たして部屋の奥からにこやかに女が顔を出して「あら、よく来たね。早くお入り」と親しげに部屋に入ることを促してくれる、その女の顔が親父と一緒に亡くなってしまった母親でという話。
12歳で両親を亡くして以来、ずっと祖父母や叔父さん夫婦に育てられてここまで生きてきた男が、50近くなって、自分よりも年若い両親と、2人だけで暮らす部屋に招かれて再会するといった話が思い出されてくるんですよね。
なんでしょうね、自分が住み慣れた色濃い記憶のある実家で再会するというのではないという、そのシチュエーションが余計に、お互い「あれからどうしてた?」という穏やかさを連れてくるようでね。過去に戻って会うんじゃない、今という地点でお互い再会するというところがね、なんとも心慰められるんでしょうね。
そんなあるはずもないことが、それでも、あったとしても不思議はないと、私にはやっぱり思えてしまうんですね。
私が昔から怪談話が好きな理由も、きっと、この辺りにあるのかもしれませんね。
(2021年11月17日 嬉野雅道)