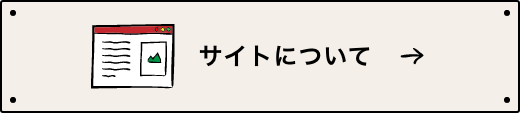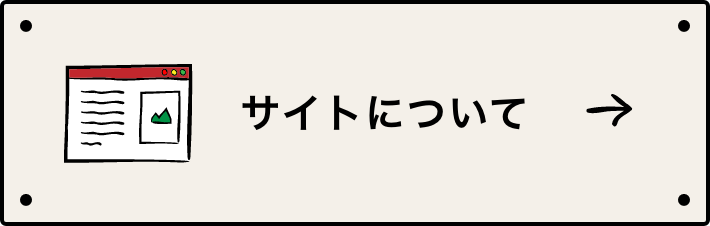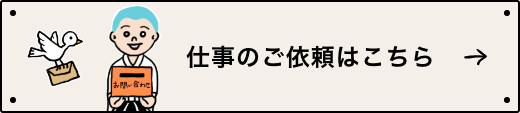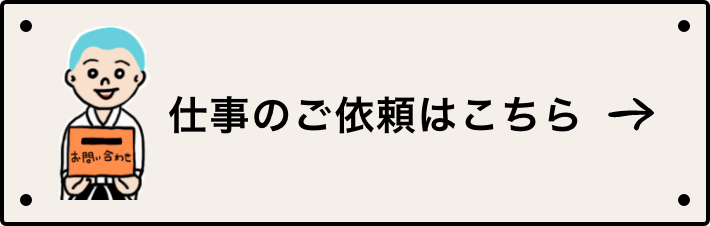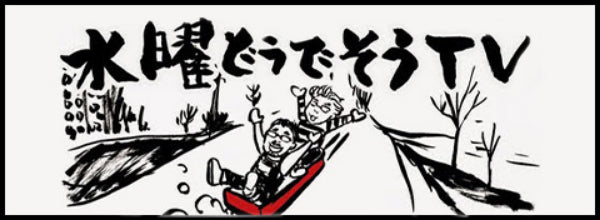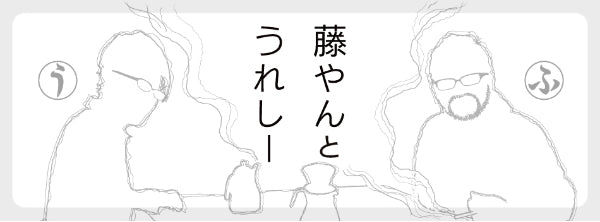おもしろみ(D陣日誌:嬉野)
(2024年12月15日)
嬉野です。日誌です。
札幌は、すっかり冬になりました。
なんとも寒い。
私も、よるとしなみで筋肉量も減りまりましたんでしょうか寒さも堪える。
会社に出ましたら「今、社内でインフルエンザが大流行なんです」と上も下もこぼしてました。
だったら社を上げてリモートにすれば良いじゃないですかと発言してみますと、不意を突かれたように一瞬黙って。
「ですよね〜」という言葉が虚しく宙を舞うばかり。
リモートにする気はないのね。
そうかといえば、風邪を引いて「まだ少し具合が悪いんです」と言いながら会社に出てきてる人もいたりして。みなさんコロナを経験したばかりのはずなのに、「まだ、ここは昭和か」と、なんだか銘々のそのスタンスが心配になってくるわけです。
そんな中、私は私で久々に会社でカフェを始めようかとフリースペースに道具を広げたところ。
誰も来ない。
いや、来ないというのか。
なんでしょうね。ひとっ子ひとり歩いてない会社なんですね。HTBってとこは。社内をね。
みんなデスクにへばりついてる。
お昼もみなさん自席でお弁当食べてるんですって。多忙なんですね。
なので、誰もフリースペースに来ない。広くて明るくて見晴らしがいいのに。
HTBが南平岸にあった頃は社屋が山頂の斜面に立つ年代物でしたから、その造りといったら田舎の温泉場の老舗湯治宿めいていて。1階だと思って入ったら2階だったとかね。建て増しに次ぐ建て増しだったこともあって他部署に行くにも自分の部署に戻るにも幾つもの部署を通過して社内を回遊するしか順路がなかった。だから、日長1日人の波を掻き分けて歩いてました。なので勢い、いろんな人とすれちがったものでしたよ。
それが今の社屋は立派過ぎるもんだから、どの階でエレベーターを降りても静まりかえった廊下が各階にあるだけで、辺りは無人倉庫のようにシーンとしているんです。
各部署には人がたくさんいるのに、そこは大きなドアで閉じられた向こうにあるので、かつての自然回遊とかには、もはや、なり得ようもない。
その上、だれもが自席でお昼弁当まで食べてるとなると、トイレに行くとか喫煙に行くとかない限り誰ひとひ廊下に出ようともしない。
となれば、あんなフリースペースで待っていたところで誰もこない。
だからまぁ、あのフリースペースにStarbucksさんとかタリーズさんとか有名カフェを入れたら、きっとみんなそれを目当てにして出て来る理由も出来るんでしょうけど、今のところフリースペースには自由しかないから誰も来ない。
まぁ、そんなわけで、そんなフリースペースで、スタバでもないタリーズでもない、ただの素人の親父が珈琲の道具を広げてカフェだカフェだと言ってみたところで、誰もこない。
たまに徘徊してる顔見知りがひょっこり来ると今度は腰が重くて帰らないから他の知らない顔が寄り付けない。
まぁ、むずかしい。
いや。というか。
違うの違うの。
そういう話じゃないのよ。
そういう話をしようと思って書き始めたわけではないのに、こんなとこまで来ちゃってて今自分でびっくりしてるんだけど。
そんな話じゃないんです。しようと思ったのは。
実はこの前、出張のときにJALさんに乗って羽田へ向かったんです。
そうそう。この話を書こうと思ってたの。会社の話はいいの。これ以上、当てもないから。するのはJALさんの話ね。
今ね。JALさんの機内で、「水曜どうでしょう」の八十八ヶ所1を視聴することができるんです。
最近の私と藤村さんの2人が前枠で少し喋ってから1999年にロケした本編の彼らに振って始まるような構成なんですが、なにしろそのあと始まるのが今から25年も前の日本を舞台にした「水曜どうでしょう」ですから大泉洋さんは若いし、画面だって正方形だ。
それに、「八十八カ所1」なんてね、もう何回見たかわかりませんよ私。
でもまぁ、羽田に着くまで私も暇ですし、機内で「水曜どうでしょう」を見るのも珍しいし、「どれどれ。。。」と見始めましたら😊これが、やっぱり見ちゃう。そして笑ってしまったの^^)
1番最初の八十八カ所と言えば、アレで1本作る気もなかったんですよね。
アレはほら、「クイズ・試験に出るどうでしょう」で、罰ゲームとして、大泉洋さんに八十八個の寺の名前を門前で叫んでもらうというだけの企画で、それを1番から88番まで全部直結で繋げて1分くらいのものにしようとしたんですね。でもねぇ、わざわざ四国に寄り道するわけですし、実際に88寺を回らなきゃ撮れないわけですから、それだけの時間はどうしたって必要になるなわけで。
「だったら、もったいないから回していこうよ」
と、いうことになりまして、徳島へ向かう機内で番組にすることにした。
それで、やってみたら😊やっぱりおもしろかったんで、そのあとシリーズ化となりましたけど。
でも、うちの番組の常として、シリーズ初手の作品というのは、中身が、あっさりしてることが多いですね。
このときの「八十八カ所1」も初手でしたから、たった2話しかないのね。
びっくりした。
実にあっさり。
勿体無いくらい。
しかし、あっさりのお味もあっさりでまたそれなりによろしいのでね、私は好きなんでございます。
それで、見てたらやっぱりついつい笑っちゃってね(^^)。で、見終わったあと思ったんです。
「これって、いつか、見てても笑えないってときってのが、くるんだろうか?」って。
だって、今だって私、相当見てる状態なんですよ。それなのに、見たらやっぱり笑っちゃうでしょ。
これが、見ても「笑えない」なんて、それって日本にどんなことがあったときなんだろうって、思えて。
それ考えたら、笑えなくなるタイミングが思いつけなかったわけです。
まぁ、この先で、私の脳が乱れてね、見てるにもかかわらず、あの人たちの「言ってることが分からない」ってなったら、そら笑えないかもしれないけど、でも話してることがわかる以上、私は、やっぱり笑いそうでね。
いや、もちろん、どうでしょう見たって笑わない人は既にいると思いますよ。
「どこがおもしろいんですか?」
みたいにね。でも、そういった人は最初から番組とソリが合わない人であるわけですから。もちろんそんな人は昔からたくさんおられるはずです。
あと、この頃は、「DVDは買っても本編は見ない」って人もたくさんおられるそうですけど。でも、見ちゃったらやっぱり笑うんだろうと思うんです。
ですから、この頃見ないとか、そういうんではなくて。
見てて、「昔は、おもしろく笑っていたのに、なんかこの頃、まったくおもしろく思えなくなってきた」みたいなことになるってタイミングって来るものなのかしらと思えたんです。
だって私、25年も見続けててまだ笑っちゃうんですからね。
でもそうだ。さすがにこの先、200年くらい経ってしまったら笑えなくなってるかしら?と思ってみたんですね。
つまりそれは、私はもうあの世に行っちゃってますから、私じゃなくて、昭和も20世紀も、平成も令和も知らない遙か未来の、でも日本語は解する人がね、見るわけですから、そんな未来人が見たら、そらもう風俗も話し言葉も違うでしょうから見ても笑えないかもしれないね、と思ったんです。
でも、江戸の昔に黄表紙という滑稽漫画本みたいなものが大評判になったことがあって。で、当時の黄表紙が今に残っているわけですよね。で、これをね、大学の先生の書かれた本で昔々読んだことがあって。そしたら、読みながら笑えたんですよ。
お話に出てくるのは、全員ちょんまげヘァーの江戸時代の人物ばかりですよ。話し言葉も江戸時代のものですよ。その人らが江戸の社会の中で、当時の風俗と当時の価値観とで現代の漫画のように絵とセリフとナレーションとで喋くってるのを未来人の私は文章とイラストの挿絵でマンガ読むみたいに読み進めたわけです。
私が読んだのは、260年も前の黄表紙でしたが、でも、これが、未来人である私にも普通におもしろく読めるんですよ。
もちろん爆笑はしないけど、でも、おもしろみは今でも充分にわかるし落語みたいだから読みながらいろんな個所で心のうちで薄く笑えるの。
お金にまつわるテーマだったんですよね。江戸時代なんて身分社会ですから、そらもう驚くべき格差社会だったでしょう。ですから、「金なんか汚ねぇものだ」という貧乏人の痩せ我慢みたいな建前が昔はあって。
だから「江戸っ子は宵越しの銭は持たねぇ」みたいな見栄を張るとかね。
貧乏を讃えるように「清貧」と言ったりとかね。
反対に大金持ちを「守銭奴」とか言って、昭和の頃までは軽蔑してましたけど、今は死語になってますから随分前から社会は守銭奴の天下になったものと思われますね。
とはいえ、江戸時代だってどんな貧乏人だってそりゃ金は欲しかったし、贅沢というものだってしてみたかった。
それは本音です。
その辺りの感じは立川談志さんの落語あたりから垣間見ることができますよね。「黄金餅」とかね。「富久」とか。
江戸の貧乏人はお金がないからと、暮らしが立たないからと、泣く泣く娘を売って金に変えるとか。げに恐ろしき時代だったわけですから、「金が仇(かたき)の世の中で〜」と芝居のセリフになったりもしてるんですね。
落語で言えば「文七元結」とかね。
それでも、というか、だからこそというか、庶民は金をため込んで金貸しとかやってる商人を嫌ったんですね。
だから、誰いうとなく、「金なんて汚いものだ」という建前が出来た。
その建前のはずの「金は汚い」を、当時評判のマンガ本、黄表紙が本音に置き換えて書いてみた。
つまり、江戸の皆さん全員が、本気でお金はうんこみたいにバッチいものだと、もし思っていたら、みんなの暮らしはどんなものになるんだろうというifの世界ですね。この社会とは価値観で逆を行く鏡の世界。
そんなテーマの黄表紙があって。
その鏡の世界では、とにかくみんな金は汚いと本気で嫌ってるから、身につけたくもない。
そこね、巾着(きんちゃく)切りと言えば今のスリのことなんですけど、そうじゃなくて、反対に他人の懐に知らぬ間にずっしりと小判の入った巾着を放り込むという、巾着切られというのが横行して江戸の皆さんは戦々恐々としている。
「冗談じゃねぇぞおっかぁ!」
「どうしたんだいおまえさん」
「おらぁ、うっかりしてて、今、懐に手を入れてみたらオレのじゃない巾着が入っててよ」
「あら、やだ」
「しかも、開けてみたら中から小判で50両だよ」
「なんだって!早くドブへでも捨てておしまい!汚らわしいねぇ」
いっぽう大きな商家では、主人が浮かぬ顔で帰ってくる。心配した番頭が寄ってきて、
「旦那様、どうされました浮かぬ顔で」
「ちょっと油断しておったら、また儲けてしまったよ」
「なんと旦那様恐ろしい!」
「オレは今日ほど自分の才覚を恨めしく思ったことはない。いっそ首でも括ろうか」
「困りましたなぁ。年の背なのに、うちの蔵はもう金が入り切らぬほどでございますのに、その上にとは。。。」
金持ちが、金があることでみんな頭を抱えているわけですね。
道ゆく江戸の民衆が、話してる。
「おい、あそこの蔵、そうとう金を詰め込んでるぞ」
「ホントだ!金がうんうん唸ってやがらぁ」
というイラストが描かれてて、それをみると、蔵から「う〜ん。う〜ん」という苦しそうな唸り声が漏れている。
「金なら唸るほどあるぁ」という、そんな言い方も昔はありましたけど、今はもう言わないのかしらね?
で、それに気づいて道ゆく人らが「あの店は金なんか貯め込みやがって」と、銘々に鼻を摘んで店の前を小走りに駆け抜けたりするから、その店の主人も奉公人も世間に顔向けができず居たたまれない。
そんな江戸で1番ストレスがないのが、金なんか持たない当時のホームレスの皆さんで、この人たちが橋の上に集まって、「まことに我々ほど清々しい身の上はこの世には御座りません」と論語の講読とかしている。
こうした江戸人の徹底したお金嫌いに「素晴らしい!」と天の神様が感じ入ってしまったんですね。
そこで、
「ひとつ、褒美をとらせよう」
ということになったんだけれども、何を間違ったか、神様は、天から大判小判の雨をざんざと降らせたものだから、それに驚いた江戸のみなさんは、「やれ、汚らわしや」と傘を刺して、首をすくめて、降りしきる大判小判の黄金を避けながら歩くというのが、落ちでね。そのシーンのイラストも描かれている。
なるほど〜と私は実に感心したわけです。
260年も前の作品なのに、おもしろさは、まだ作品の中で生きているんです。
これはすごい。
だったら、「水曜どうでしょう」はどうだろう。こっちは動画だし、発声してるから、リアルにおもしろげな言いっぷりで喋くってるその人間を、目のあたりに見れてしまうわけだから、おもしろさの命という上では黄表紙よりも、もっともっと長いのではないだろうかと思えたのです。
おまけに「水曜どうでしょう」は放送を始めた当初から、番組を見た人が全員、「誰?この人たち。。。知らない顔の人ばかりだけど。それに、なに?この人たち。いったい何がしたいの?」というふうに、疑問と違和感を入口として中に入るしかないことを前提として予め作られていたわけで。
これは、未来人が見るときもまた、「え?誰?この人たち?え?何してるの?」という、入口としては同じ違和感から入るだろうことを思えば、そうした入り口から招じ入れることで既に成功しているだけに、「水曜どうでしょう」は、現今の他の有名なメジャー番組と比べても遥かに有利なのではと思えてくれば、500年くらいはおもしろみも生き続けることであろうよと思ったものでしたよ、という。
まぁそれだけの話ですね。
お後がよろしいようで。
だめですよ、私の書いたもの、最後まで読んじゃ。結論ないんだから〜〜